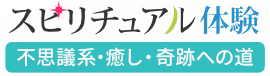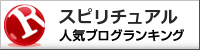世界に誇れる日本の「和の精神」。この太古から続く日本人の精神性は素晴らしい一面を持っていると思います。
しかし、世の中の組織を顧みてみると、必ずしも良い面だけではなさそうです。「和の精神」は閉鎖的なグループになることで弊害をも生み出すことがあります。
この記事では実例やスピリチュアル的な側面などを交えて解説しますので、「日本人の和」について深堀したい方はぜひご覧ください。
目次
日本人の和の精神には2種類がある
日本人の「和の精神」には3種類あると思います。
※私が個人的に分類したものですので、一般的に知られている分類ではありません。
① 人類全体の和・日本全体の和
② 特定の団体の和・家族の和
③ 自分たちだけ大切にして部外者を蔑ろにする少人数の和・内輪が全てな排他的の度が過ぎる和
①の人類全体の和、日本全体の和を大切にするのは素晴らしい概念であることは間違いないです。
人類全体の和の精神の概念は、宗教的にいえば大乗仏教の思想やイエス・キリストなど様々な教えの根底に見出すことができます。
また、スピリチュアルの世界では「ワンネス」と言われていますが、これこそが「和①」のことを表していると解釈することもできます。
スピ系の人が和を大切にされる場合、「和①」なのかを意識してみると良いでしょう。
サッカー競技場でのゴミ拾いや東日本大震災の後の日本人の譲り合いの精神などが世界で絶賛されますが、このような姿勢は世界や日本を大切にしようとする思いやりであり、「和①」は「世界に誇れる素晴らしい・尊い日本の和」と言っても良いと思います。
しかし、同じ和の精神でありながら、「和③」・・・自分たちの結束を優遇するあまり部外者を蔑ろにする少人数の和、あるいはごく一部の内輪がマウントを取る排他的な和となった場合、本当に「素晴らしい・尊い・世界に誇れる日本の和の精神」と言えるのでしょうか?
現在弊害があるとされる政治や制度作りの分野で問題視される様々な課題なども、問題とされる組織の一人一人はいい人である可能性はあるかもしれません。
しかし、和になったとたんに同調圧力がかかり、個人の意思が反映されずに様々な問題を起こしている可能性が十分あります。
また、一般的に「ニッポンの和の精神は尊い!」と解説されることは多いですが、そのような場合、残念なことに、この和①と和②と和③の違いを意識して解説する人は非常に少ないように見受けます。
ねじ曲がった和の精神 和の中の和という特権構造
今まで、個人的に様々な組織や団体を見てきましたが、和の中に和を作るという構造はよく見られる現象のように思います。
たとえば、ある組織があり、その中にグループがあり、さらにその中に特定のグループがあるという入れ子構造です。
「和の中の和」です。
この特定のグループは、過去に何らかしらのつながりがあったとか、同じ学校を卒業しているなどです。
ここで、一例を出してみましょう。
私があるサービス業の企業内でIT系の講師的なこと(コンサルティング)をしたときの話です。
そこで講義が終わったあとに、ある従業員の方一人と個人的に会話をする機会がありました。そのとき、彼は私にその企業内の問題をひっそりと打ち明けてくださいました。
話を伺うと、どうやらそこの職場(30人規模の大人数)は問題だらけ従業員の多くがストレスになることがあるそうで、その原因はすべてごく一部の3~数人程度のグループAによって仕切られていることに起因するらしいです。このグループAは別に偉い役職とかではないのに強固なグループを結成し、大勢のなかでマウントをとっているとの話でした。
また、その人たちには職場の改善のために何をいっても受け入れることをせず、他の従業員の意見を排除しているようです。
私に話してきたのは、なんとかこの状況を変えるために助けて欲しいという気持ちからのようです。
そのグループAのメンバーは、以前、別の企業に勤めていた仲間らしく、そのままここに移籍してきたといいます。なるほど、と思いました。
なので、そのグループAに属するごく少数の内輪の人が企業内でマウントを取り、多くの従業員は不自由を感じながら仕事をしていたといいます。かなり昔のことで細かいことは忘れましたが、サービス業としてこんな問題やあんな問題など、多数の問題を抱えているけど、すべてそこのグループが原因で解決できないとのことです。
彼は長時間そのことについて、詳しく私に話してくれました。
私も実際にこのグループAに属する方と挨拶させていただきましたが、そのグループの方は非常に愛想よく、またお仕事をしっかりされていて、第一印象はたいへん良かったです。しかし、このような問題が存在することを知ると、あまり良い印象はありません。
やはり、和③の現象がここに出ていると思います。
※グループAに事実を確かめられる機会はなく、一方的な意見なので、グループAの主張を知ればまた違った意見になるかもしれませんが、とりあえず私の知る限りの情報で判断しました。
別にグループを作ることは自然なことで、問題があるわけではないですが、オープン・フェアでない排他的なところは良くないと思います。
また、この「和③」の現象は、比較的過疎化しつつある地方のほうで見られるかもしれません。県外から来た人が「よそ者」として排除されることが問題化されることはよくある話です。
スピリチュアル的に見れば?
スピリチュアル的に見れば、他人に与えたものは時間をかけて必ず返ってくる・その報いを受けるという法則が成り立ちます。
それは、この世的の話だけではありません。死後の世界、あるいは生まれ変わりを通してという長いスパンの中でという意味です。
そういう意味で、「和③」のグループの姿勢の人は、部外者の人と同じ気持ちを味わうような出来事に、将来的に遭遇する可能性を招く、といえそうです。
なので、ある程度内輪になるのは仕方ないことですが、同じ組織内で度が過ぎる閉鎖的で部外者をあしらうグループは、カルマ的に良いものとは言えないでしょう。
一方で、部外者が迷惑をかけまくる人である場合、受け入れる必要はありません。スピリチュアル的に見れば仲間を守る必要もあるからです。
政治や宗教の話をしづらい日本の雰囲気 和の精神が原因!?
主に欧米など、外国では日常会話で政治や宗教の話をすることがごく自然の風景だといいます。
また、イデオロギーが違っても、そこで喧嘩ではなく意見の相違として受け止める人が多いようです。イエス・キリストの寛容の精神に影響を受けているためでしょうか。
一方で、日本では日常生活で政治や宗教の話がタブー視されています。万が一、政治や宗教の話をして人間関係に亀裂が入ったら?と、予め防御線を張っています。
また、その姿勢は正しいかもしれません。
なぜなら、日本人の中で「和②」や「和③」の姿勢の人が少なくないから、と私は踏んでいます。
万が一、お互いのイデオロギーが大きく違う場合、相互が違うという理解では終わらずに互いへの攻撃や排除が始まりやすい雰囲気にあるといっても過言ではありません。
とくにSNSでは外国人の方と日本人でこの傾向が顕著に違う、と言われています。
これは、日本人の根底に「和」を大切にする人が多く、それゆえに無自覚で自分の属する「和」でない奴は許さない・・・という姿勢の人が多いことから来ていると予測できます。
これからの日本は、和を作るのはいいけど、自分と違う意見の部外者にすぐに攻撃したりマウントを取ろうとする態度は避けるような方向に進化することが求められていると、私個人には思えてなりません。
公益通報者は和の精神に反する?
世間のニュースを見ると組織内部が腐敗する事件が多く、公益通報者の意義を問われることが少なくありません。
ケース・バイ・ケースによっては、公益通報者が罪を問われる、などの議論が出てきたりします。
世間一般の人の反応としては、内部通報者、公益通報者に対してたいていは「正義の存在」「よくやった!」と思う人が多いでしょう。
しかし、組織内部からすれば「和を乱すならず者」になるわけですね。
そこで、組織内の腐敗を知ってしまい、これを改善したい内部通報者、公益通報者とは、果たしてスピリチュアル的に、和を乱す人に該当するのでしょうか?
私個人の意見としては、内部通報者、公益通報者の方は「和①」を大切にするために「和②」「和③」を壊す、という姿勢を表しているように理解しています。
それを、日本では多くのケースで一般的に「和の精神は大切だ」「和を乱すのは問題だ」だの、「和」というものをひとくくりにして論じているところに問題の根があるのかもしれません。
これからの日本は、「和の精神」やら「和を持って尊しとなす」を掲げる場合、「和①」「和②」「和③」という3つの概念をしっかり見定めた上で、議論をすべき時がきている、と私は思います。
なお、「和①」「和②」「和③」という表現はわかりやすい私の暫定的な表現に過ぎませんので、もう少し愛称のある呼び方が良いかもしれませんね。
和③などは、新しい名前をつけると良さそうです。
そのほうが、第三者から指摘しやすくなるでしょう。
和の精神は、「人類規模の和」が第一にあって、そのベースの上で他の和が構築されることが望ましいですし、排他的な和よりオープンでフェアな和が理想的のように思います。
また、「和」はオープンすぎるのも閉鎖的すぎるのも問題なので、ちょうど良いバランスのオープンさが求められます。
なので、部外者への排他的な姿勢は絶対に禁止して、なんでもオープンに100%受け入れろ、という要求もまたバランスを欠いていると思います。
おわりに
いかがだったでしょうか?
様々な異なる「和」があるのに、言葉のあやから「和」として同じこととして扱われることが多いことから、日本の誇れるべき「和の精神」がある一方で、日本特有の問題の根底に「和の精神」が潜んでいることに気づいてない人が多いのではないでしょうか。
和の正しい捉え方が今後、発展することを願う次第です。